〒192-0362 東京都八王子市松木19-5-105 京王堀之内駅 徒歩12分
駐車場:近隣にコインパーキングあり (ご来所時に最寄りのグループホーム同時見学も可能です)
近隣・遠方問わず 一度も来訪せずに継続的なZoomやお電話、メールでの打ち合わせも可能です。全国対応です。
受付時間
定休日:日曜
日中支援はどこまで必要か?
日中サービス支援型を除く通常のグループホームでは、日中ご利用者が就労先または作業所へ通所することが前提で、区分が低めの事業所では常勤換算も緩いため日中のスタッフを配置しないことがほとんどです。
ただし、ご利用者が風邪などの体調不良で休んだ場合は、臨時にスタッフが日中支援に入ることがあります。責任ある支援のためには一定時間は入らざる得ないと言えます。
では、数日の体調不良では済まない、1か月を超えるような長期の日中滞在に関しての支援はどうでしょうか?
なお、土日の日中支援は運営方法によりけりですので、ここでは詳しく触れませんが、地元の方ばかりのホームなどは土日は帰宅させるホームもあります。
しかし、土日は毎週は帰宅できない方が多く、ご利用者が滞在する限り、軽度であっても日中でも支援員を配置するホームがほとんどです。ご利用者の長期利用や安全、安心面やトラブル回避のためには配置することが望まれます。

長期の体調不良は・・・
1ケ月以上の休職などへの対応
精神科病院へ入院するか救護施設に入るなどの方法もありますが、そうでない場合はグループホームで日中支援することになります。
休職中の日中支援など責任ある体制と覚悟も必要です。弊事業所はご利用者が数か月の休職中24時間体制で支援しました。日中サービス支援型への転換も検討したくらいです。
<日中サービス支援型について>
24時間支援する対象者は区分に関わらず事情があるわけですから、結果重度者を日中支援する覚悟は必要です。
日中サービス支援型は必要とされているし弊社含めて検討する運営事業者は多いと思いますが、なかなか普及しませんね。
<日中支援加算について>
令和6年4月よりそれまでは3日目からだった加算が初日から算出できるようになり、かねてより指摘されていた矛盾がひとつ解消されました。
弊社の初年度の対象ご利用者は精神1級ながら区分3でしたから日中支援加算Ⅱでした(泣)。
さすがの1級です。通院先のドクターからの助言もあり、日中支援が必要となれば24時間間断なくスタッフを配置します。私も初年度は人手不足の正月にも朝から支援に入っていました。効率だけ考えていては成り立たないですね。
例えば令和6年1月現在なら物価高騰支援補助金が出ます。何度も勝手に案内が来ます。ちゃんと貰ってくださいと繰り返し案内していただけます。他業種の一般事業会社ならほぼあり得ない支援です。この点は恵まれた業界だと思います。)
夜勤者を早めに来てもらい空白時間を少なくするとか、人件費の変わらない役員が日勤に入るとか工夫して回復を待つしかありません。こうなるとどこまで間断なく支援するかは運営者判断です。
平日の長期に渡る日中支援は、日勤者がいない状況では発生しないに越したことはありませんが、よくよく考えて採算ベースにのる人員配置、障害区分設定を考えて運営するのが最大の防御かと考えます。区分高めの利用者に入居いただくなり定員数拡大をしていくと人員配置の工夫もしやすくなります。
弊事業所では現在はむしろ、日中支援加算対象者がいないにも関わらず、区分変更で区分がかなり上がったので、増えた常勤換算分をどこに配置するかに頭を悩ましています。だから現在なら通所を休む方の対応が以前よりはスムーズに組めます。今では上記はただのネタです。苦労は裏切らないと今だからこそ言えます。
高めの障害区分であれば常勤換算に余裕が出来るため、日中の人員配置可能で日中支援の問題はかなり解決します。シフトを組んだら一目瞭然です。
なので初年度はヒヤリングの甘さにより難易度の高い利用者が入居して、平日は日勤者(日中配置がない)がいない状態にも関わらず、ご利用者が就労先(特例子会社)を休まざる得ない状況となり寝込んでしまったため一定期間(4カ月)24時間支援を強いられました。
現状では制度が完ぺきとは言えず制度の漏れを「善意か責任感か正義感か・・」何かで埋めているのが現在の福祉業界です。より良い制度とするためには声を上げましょう。
ご利用者様の安定はご家族の喜びでもあり、それが毎月のコミュニケーションで伝わってきます。
部分的なマイナス要素だけでなくそういう側面も考慮して全体最適で判断しましょう。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

初回45分 無料相談実施中!
近隣・遠方問わず 一度も来訪せずに継続的なZoomやお電話、メールでの打ち合わせも可能です。全国対応です。
| 受付時間 | 10:00~19:00 |
|---|
| 定休日 | 日曜 |
|---|
お気軽にお問合せください
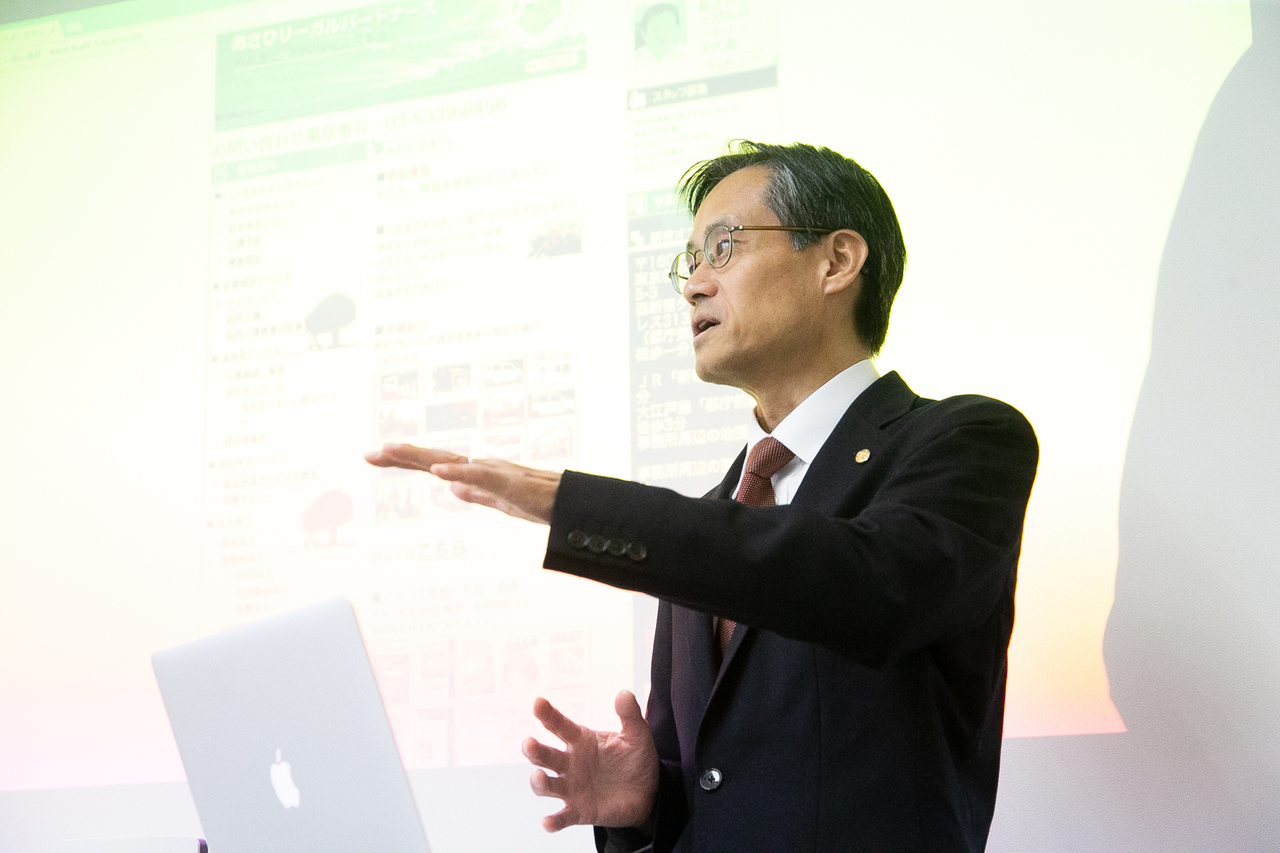
お電話でのお問合せ・相談予約
初回45分 無料相談実施中!
<受付時間>
10:00~19:00
※原則日曜除く
質問フォームは24時間365日受付中です。お気軽にご連絡ください。
近隣・遠方問わず 一度も来訪せずに継続的なZoomやお電話、メールでの打合せも可能です。
ただし、現地確認は必ず私が直接行います。
全国対応です。
新着情報・お知らせ
「専門職採用(看護師)のシミュレーション」を更新。
「区分決定前の利用方法」を更新しました。
「入居者の受け入れに関する障害区分の重要性」
~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
および
その2、その3を追加。
代表者あいさつを3部構成へ修正
およびマスコミ掲載実績
を追加
「入居者の受け入れに関する障害区分の重要性」
~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
「クライアント開設例」
を新たに掲載
「区分決定前の利用方法」について更新(体験入居のケースを追記)
「グループホームでの生活費」を修正(年金額改正、体験入居等追記)
「アパート・マンション個室ワンルームタイプ(軽中度)の開設・運営方法」及び「総量規制の現状」を追加予定
サイドメニュー
- 運営の実際
- お役立ち情報
障がい者グループホーム
開設運営ナビ

住所
〒192-0362
東京都八王子市松木19-5-105
アクセス
京王堀之内駅 徒歩12分
駐車場:近隣にコインパーキングあり
近隣・遠方問わず一度も来訪なしに継続的にZoomやメール、お電話での打合せ可能です。
ただし、現地確認は必ず直接行います。
全国対応しております。
初回 45分 無料相談実施中
受付時間
10:00~19:00
定休日
日曜
